 子どもの行動理解
子どもの行動理解 自閉症の一平君モスバーガーのメニューを作る
おおぎやラーメンのメニュー作りに続いて、一平君の大好きなモスバーガーのメニューを作りました。モスバーガーの広告やポスティングが手に入らないので、おおぎやラーメンの時と同様に、パソコンからプリントアウトしたものを使います。...
 子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解 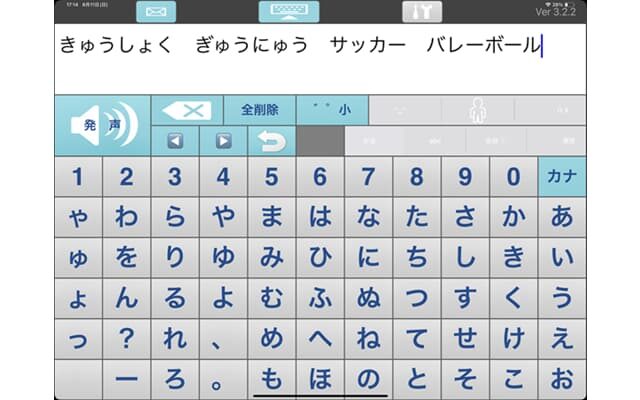 子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解 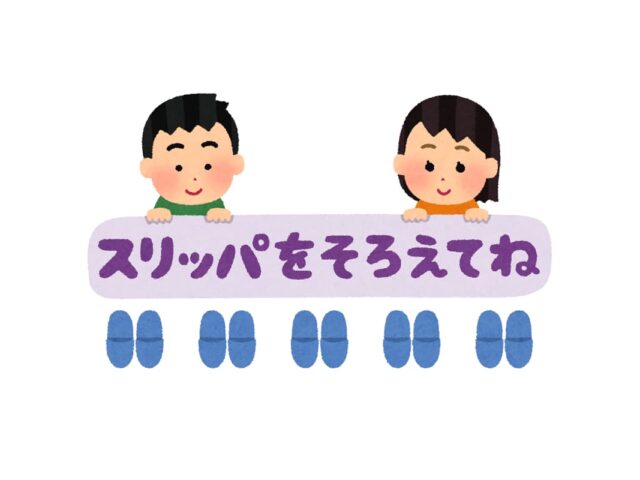 子どもの行動理解
子どもの行動理解 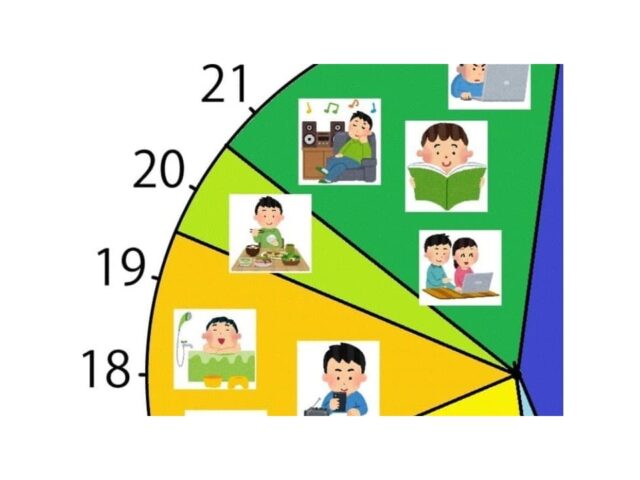 子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解  子どもの行動理解
子どもの行動理解