発達障害とくくらずに、「子どもの行動理解」を、2020年11月から投稿して来ました。
「発達障害」とある方が、検索して読みやすいというご意見を頂いたので、関連している投稿を年齢順にまとめます。
今回は、小学生の行動理解が中心です。
1.子どもの行動の意味を読む
2.確定域で付き合う
3.初対面の子どもの現勢の保障
4.支援者の23のポイント
5.たたく行動の意味
6.主語は子どもの心、常識が主語ではない
7.発達障害児は苦労から心が荒れやすい
発達障害児は保育園での苦労から小学校へ入学するまでに気持ちや態度が荒れている場合がある
8.小1ギャップの乗り越え方
9.行動調整を目に見せるTOSSかるた教材
10.保育園文化と学校文化の違いが分からない1年生
席に座る、黙って聞く、友達の気持ちを考える、が難しい小学校1年生の環境調整
11.授業参加が難しくなった2年生
気持ちを話せない登校を渋りがちの子どもの授業参加が難しくなった理由を探る
12.教室離脱に対応する方法
13.回避行動・共感・緩衝行動
14.物理的な環境調整(掃除当番)
発達障害児のソーシャルスキル指導では精神論を持ち込まないで物理的に工夫する方がうまくいく
15.物理的な環境調整(給食当番)
カレンダーを手がかりにして、暦についての会話や、給食当番を意識する方法
16.持ち物シート
言葉で伝えやすくする 画像を使ったコミュニケーションシートの作り方
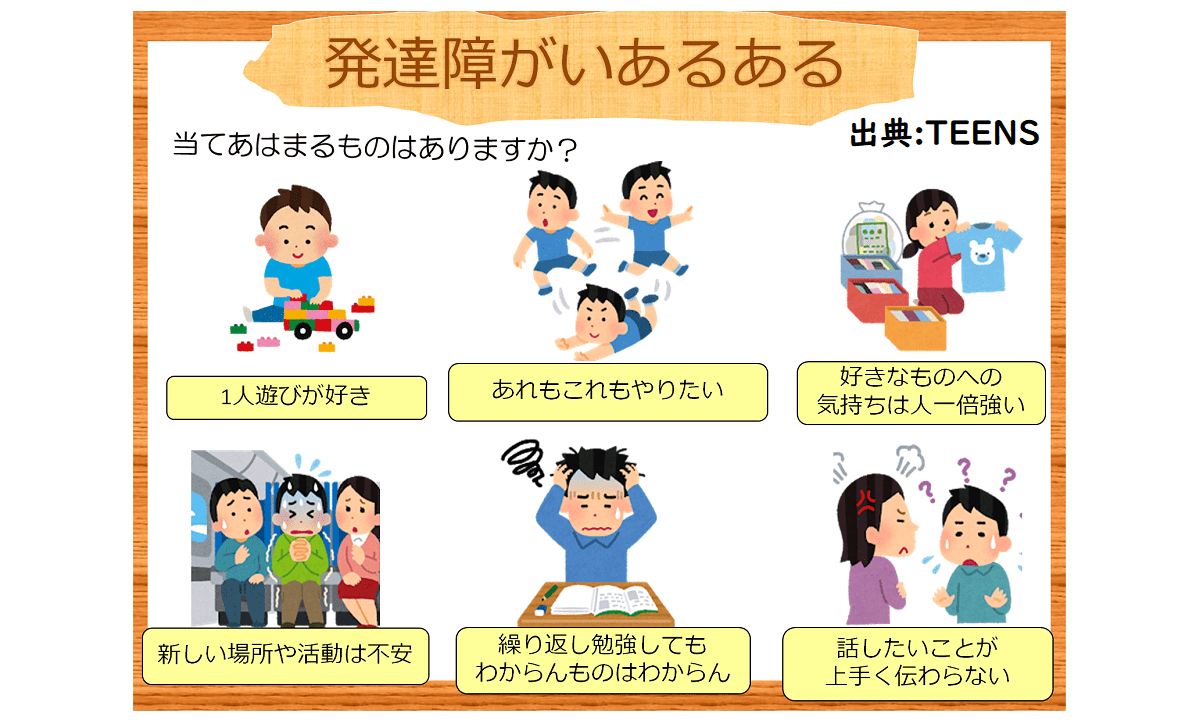
猫ちゃんブログへのコメント